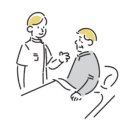外国人が日本で働くためのビザとして最も一般的なのが「技術・人文知識・国際業務」の在留資格です。2018年12月の調査において、225,724人もの外国人が「技術・人文知識・国際業務」を所持しています。これは日本に在留しているすべての外国人(総数2,731,093人)の約1割を占めており、就労目的の在留資格をもつ外国人(350,680人)の約3分の2にあたります。
エンジニア、ホワイトカラーの職種をほぼカバーしているので、会社で働く際に最初に選択肢となりうる在留資格です。もともと技術と人文知識・国際業務は別々の在留資格だった経緯もあり、ひとまとまりに考えるのではなく、3つをそれぞれ個別に捉えた方が正確です。ここでは、国が定めている基準に則った形で「技術・人文知識・国際業務」のビザについて詳しく説明します。
なお、kedomoは外国人専門の人材紹介会社です。高度人材・特定技能採用、登録支援機関の依頼を検討中の企業様はぜひご相談ください。
目次
1.就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の入管における審査ポイント
「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得できる基準として、国は入管法や上陸基準省令、入国・在留審査要領等を定めています。大きく分けて5つの審査ポイントを挙げることができます。
①自然科学・人文科学の技術・知識を必要とする業務に従事する活動であること
「技術・人文知識・国際業務」の業務内容は入管法で下記のように規定されています。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動 |
技術に該当する部分は、理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務です。人文科学に該当する部分は、法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務と書かれています。
国際業務に該当する部分は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務と規定されており、技術・人文知識の内容とは若干異なるので注意が必要です。後述するように、国際業務は学歴要件、経験実務要件において、他の2つとは異なる基準があります
「未経験可、すぐに慣れます」と募集広告に記載のあるような専門性の低い業務内容や、後述する②の要件を満たさない日本人従業員が一般的に従事する業務内容は、対象とならないとされています。(入国・在留審査要領第12編より)
②一定の学歴要件、又は一定年数以上の実務経験を有していることにより、従事しようとする業務に必要な技術又は知識を修得していること
技術・人文知識の場合、下記のイ、ロ、ハ、但書のいずれかを満たしている必要があります。
≪技術・人文知識≫
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。 ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。 ハ 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む)を有すること。 但書 申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で,法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは,この限りでない。 (上陸基準省令より) |
学歴要件として、①日本又は外国の大学を卒業しているか、それと同等以上の教育を受けていること、又は②日本の専門学校を卒業していることが必要となります。
①のそれと同等以上の教育を受けているとは、具体的には、短期大学卒業も含まれます。中国を例にすると、大学(又は学院、うち本科・専科を含む)、専科学校、短期職業大学が該当します。
業務に関連する科目についての判断基準ですが、これは大学と専門学校で基準が異なります。大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性は、比較的緩やかに判断される一方、専門学校の場合はより厳格に審査されます。
但書の部分は、IT技術者の受け入れのために規定されています。該当する情報処理の資格は法務省webサイトよりご確認いただけます。
≪国際業務≫
国際業務の基準は、≪技術・人文知識≫のイ、ロを満たすか、下記の条件を満たすことのいずれかが必要となります。
従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。 (上陸基準省令より) |
国際業務は実務経験要件が3年となっている点がポイントです。実務経験は、海外において「関連する業務について」のものであれば良く、外国人が日本で従事しようとする業務そのものの実務経験まで必要とはされていません。
学歴要件については、≪技術・人文知識≫のイ、ロが適用されるため、①日本又は外国の大学を卒業しているか、それと同等以上の教育を受けていること、又は②日本の専門学校を卒業していることのいずれかが必要です。(入国・在留審査要領より)
③日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
個々の企業の賃金体系を基礎に日本人と同等額以上であること、また、他の企業の同種の職種の賃金を参考にして日本人と同等額以上であることが必要です。この場合、外国人が大卒であればその企業の日本人大卒者の賃金を、専門職、研究職であればその企業の日本人専門職、研究職の賃金を参考にします。
通勤手当、扶養手当、住宅手当等は賃金に含みません。
④素行が不良でないこと
これは在留資格変更許可申請の際の基準となる項目です。
留学生が資格外活動の条件に違反して、1週間に28時間を超えるアルバイトをしている場合などが該当します。
⑤入管法に定める届出等の義務を履行していること
この項目も在留資格変更許可申請の際の基準となります。
在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務をきちんと履行していることが必要です。
2.就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」申請のための必要書類
申請しようとする外国人が、日本にいるか海外にいるかで手続き内容が異なりますが、必要書類はほぼ同じです。日本国内にいる場合の手続きは「在留資格変更許可申請」、海外にいる場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
雇用先の企業の規模や種類により、4つのカテゴリーに分類されています。
| カテゴリー1 | (1) 日本の証券取引所に上場している企業 (2) 保険業を営む相互会社 (3) 日本又は外国の国・地方公共団体 (4) 独立行政法人 (5) 特殊法人・認可法人 (6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人 など以下省略永住権 |
| カテゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人 |
| カテゴリー3 | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
| カテゴリー4 | 上記のいずれにも該当しない団体・個人 |
【必ず必要となる書類一覧】
1 在留資格認定証明書交付申請書 又は 在留資格変更許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 返信用封筒(宛先明記の上、404円分切手を添付) 1通
4 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)など
カテゴリー2および3:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
5 専門士の資格を証明する文書 1通
———以下はカテゴリー3、4のみ必要———
6 労働条件明示書 1通
7 学歴又は職歴等を証明する文書 卒業証明書など 1通
8 登記事項証明書 1通
9 事業内容についての案内書 1通
10 直近年度の決算文書の写し、決算文書がない場合は事業計画書 1通
———以下はカテゴリー4のみ必要———
11 法定調書合計票を提出できない理由を明らかにする資料
【申請の際に添付しておいた方が良い書類】
〇申請理由書(雇用理由書ともいう)
〇業務内容説明書及び一日のスケジュール
上記2つの書類を1つにまとめて、申請理由書として提出する場合もあります。就労ビザの申請において、すべての立証責任は申請人側にあります。申請人がとても優秀で勤勉な人間であろうと、審査官に伝わらなければ意味がありません。これらの書類は、そういった情報を審査官に伝えるための補足資料の性格を持ちます。
特に審査ポイントとして挙げた5つの項目のうち、
①自然科学・人文科学の技術・知識を必要とする業務に従事する活動であること②一定の学歴要件、又は一定年数以上の実務経験を有していることにより、従事しようとする業務に必要な技術又は知識を修得していること
この上記2つは細かくチェックされます。具体的にどんな業務に従事するのか、そしてその業務内容と学歴が一致していることを、きちんと説明しましょう。①は、一日のスケジュールまで落とし込んで説明すると、より説得力が増します。
3.就労ビザ「技術・人文・国際業務」で就ける職種
技術・人文知識・国際業務のビザで就ける職種は決まっています。 重要となるのは活動内容です。
技術
自然科学の分野に属する知識を必要とする業務に主として従事する活動と規定されています。具体的には、製造業などのエンジニア(技術者)やIT系のプログラマー、設計などが該当します。
類似する在留資格として「研究」がありますが、「研究」は技術等の研究をすること自体を目的とする一方、「技術」は知識・技術を用いて業務の遂行に直接資する活動である点で異なります。
人文知識
人文科学の分野(いわゆる文科系の分野で あり、社会科学の分野も含まれる。)の知識を必要とする業務に主として従事する活動と規定されています。具体的には、総務、経理、マーケティング、企画などが該当します。
国際業務
上陸基準省令に規定されているように国際業務で就ける職種は、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務となっています。
4.就労ビザ「技術・人文・国際業務」の有効期間
ビザの有効期間は4種類あり、3か月、1年、3年、5年です。
どの在留期間が付与されるかは、入国・審査要領により基準が定められています。 もちろん更新は可能です。
5.就労ビザ「技術・人文・国際業務」での家族帯同、永住権
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人は、配偶者・子を日本に呼ぶことが出来ます。両親や叔父などの親族を呼ぶことはできないので、注意してください。
配偶者・子の在留資格は家族滞在となり、日本での就労は原則として認められていません。しかし資格外活動許可をとることにより、週28時間以内のアルバイトをすることができます。
また日本で永住権をとりたい場合は、他にも要件はありますが、日本での在留期間10年以上、そのうち「技術・人文知識・国際業務」のビザで5年以上在留していれば、永住権を申請することができます。
家族帯同、永住権の詳細については、コラム『外国人エンジニアが家族を日本に呼び寄せる方法』、『外国人社員が永住権を取得するには』をご覧ください。
6.外国人採用はkedomoへ
「技術・人文知識・国際業務」ビザについて解説しました。申請する際に必要となる書類は、個々のケースにより異なることがありますので、念のため入管に事前確認されることをおすすめします。
kedomoでは人材募集から面接、来日時の生活サポートまで、求人がスムーズにいくようしっかりとサポートしています。エンジニア採用はもちろん、人手不足業界を助ける「介護」「養殖業」「造船」「製造」「外食」「宿泊」などの特定技能業種の採用も登録支援機関として力を入れて支援しています。外国人採用をご検討の際は気軽に声をお掛けください。
<この記事に関連するページ>
『初めての外国人採用』
『外国人エンジニア採用』
『登録支援機関の業務』
<参考資料>
e-Stat 在留外国人統計(旧登録外国人統計)
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
法務省 留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン